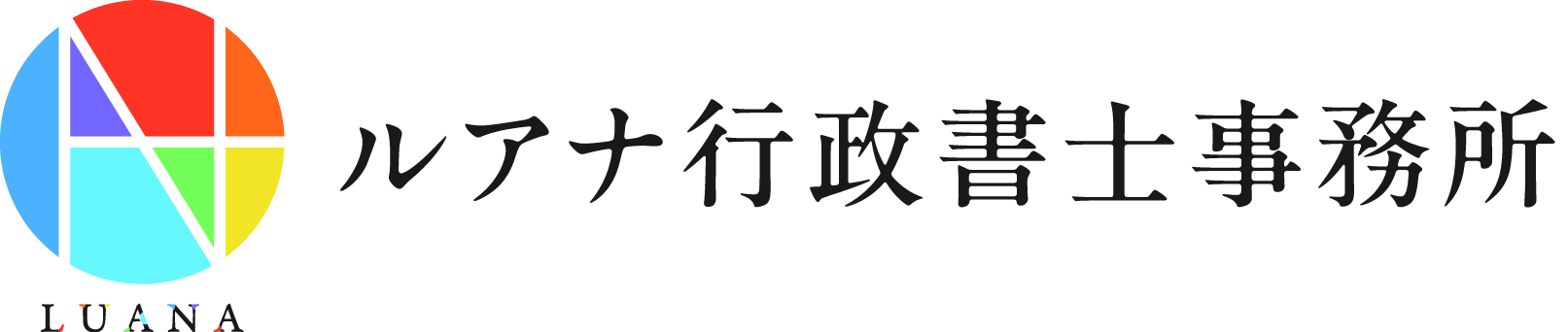建設業許可申請

建築一式工事を除き、請負金額が税込500万円以上となる建設工事を行う際には、この許可が必要になります。
許可の有効期間は5年間です。許可日から起算して5年後の許可日前日までが有効期間となります。引き続き建設業を営む場合は、期間満了の30日前までに更新手続きを行う必要があります。更新を怠ると、軽微な工事を除いて建設業の営業ができなくなります。
許可について
許可の種類
建設業許可は、営業所の所在地に応じて「国土交通大臣許可」または「知事許可」に分かれます。
| 国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所がある場合に必要です。 |
|---|---|
| 知事許可 | 1つの都道府県内にのみ営業所がある場合に該当します。 |
許可の区分
| 一般 | 下請けとしてだけ営業する場合、または1件の元請工事につき、下請けに出す代金の合計金額が5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)の場合 |
|---|---|
| 特定 | 元請業者で、1件の元請工事につき、下請けに出す代金の合計金額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)となる場合 |
許可基準要件について
建設業許可を取得するには、以下のような基準を満たしていることが求められます。
- 経営業務管理責任者の要件
- 営業所技術者の要件
- 誠実性
- 財産的基礎等
ご依頼までの流れ
ご面談
許可申請にあたっては、面談のうえ資料をご確認させていただき、ご状況に応じたご説明をいたします。
ご希望の場所までこちらからお伺いいたします。
お見積
お見積りの提示と、必要書類に関するご案内をさせていただきます。
申請書類の作成
ご依頼をお受けした後、必要書類をお預かりし、申請に必要な書類を作成いたします。
行政へ申請手続き
申請先の行政機関への書類提出は、当事務所が代理で行います(※手数料の実費がかかります)。
書類等の返還
提出した書類の控えと、お預かりしていた原本類をご返却いたします。
許可通知
申請の受付から2か月程度で、許可通知が発送されます。
許可後のお手続き
許可取得後の各種手続きについても、当事務所が責任をもってサポートいたします。
- 事業年度終了届
毎事業年度終了後、4か月以内に提出が必要です。 - 経営事項審査申請・入札参加資格審査申請
公共工事を請け負うためには、申請が必要となります。 - 許可更新手続き
5年ごとに更新手続きを行います。 - その他の変更届
商号や役員の変更など、必要に応じた各種届出が求められます。
| 業務内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 建設業許可(新規)・知事許可申請 | 132,000円~ |
| 建設業許可(新規)・大臣許可申請 | 220,000円〜 |
| 建設業許可(更新)・知事許可申請 | 77,000円〜 |
| 建設業許可(更新)・大臣許可申請 | 99,000円〜 |
| 決算変更届の作成・提出 | 38,500円〜 |
※上記は目安です。正式な金額はお見積もりにて提示いたします。
※申請手数料などの実費は別途必要です。
※遠隔地訪問や証明書取得代行には別途実費がかかる場合があります。
宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業を始めるには、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事から免許を取得する必要があります。
免許の有効期限は5年間で、更新手続きを忘れてしまうと大きな支障となります。業務を継続的かつ安定的に行っていくためにも、当事務所がしっかりとサポートいたします。
宅地建物取引業とは
- 宅地または建物について自ら売買または交換することを継続して業務として行うこと
- 宅地または建物について他人が売買、交換、貸借するについて、その代理もしくは媒介することを継続して業務として行うこと
サポート内容
当事務所では、免許申請のお手続きはもちろん、宅建協会への加入手続きについてもサポートいたします。
免許の種類について
- 国土交通大臣の免許
2つ以上の都道府県に事務所を設置している場合 - 都道府県知事の免許
1つの都道府県内のみに事務所を設置している場合
| 業務内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 宅地建物取引業者免許申請(新規) ※宅建協会入会の手続きを含む | 150,000円~ |
| 宅地建物取引業者免許申請(更新) | 90,000円〜 |
※上記金額は目安です。正式な金額はお見積りにてご提示いたします。
※申請手数料などの実費は別途必要です。
会社設立・NPO法人設立

当事務所では、会社設立やNPO法人設立に関する手続きを、初めての方でも安心して進められるようお手伝いいたします。法人を立ち上げる際には、定款の作成や必要書類の準備など、法務局や所轄庁への申請に向けた手続きが多数あります。
法人形態の選び方
事業内容や目的に応じて、最適な法人形態をご案内いたします。株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人(特定非営利活動法人)など、複数の選択肢から、お客様に合った形態を判断します。
株式会社・合同会社・一般社団法人設立
株式会社・合同会社、一般社団法人は、設立手続きの流れや必要書類が異なります。
- 株式会社・一般社団法人:定款認証が必要です
- 合同会社:定款認証不要で、より簡便に設立可能です
登記手続きは提携司法書士にてワンストップで対応いたします。
初めての方でも安心して設立できるよう、手続き全体を丁寧にご案内します。
NPO法人設立(特定非営利活動法人)
NPO法人は非営利活動を目的とした法人で、所轄庁への設立認証が必要です。設立趣意書や事業計画書、予算書などの作成も求められ、内容の整合性が重要です。
当事務所では、書類作成から所轄庁への申請まで一貫して対応いたします。
| 業務内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 株式会社設立 | 66,000円~ |
| 合同会社設立 | 55,000円〜 |
| 一般社団法人設立 | 66,000円~ |
| NPO法人設立 | 198,000円~ |
※上記金額は目安です。正式な金額はお見積りにてご提示いたします。
※定款認証手数料・登記費用・登録免許税などの実費は別途必要です
産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業を営むには、許可の取得が必要です。運搬方法には、排出先から処分場まで直接運ぶ直行型と、途中で積替えや保管を行ってから運ぶ方法があります。
申請を行う前には、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。
許可の有効期間は5年間です。期限までに更新手続きを行わないと許可は失効してしまうため、早めの準備が大切です。また、運搬元と処分先の自治体が異なる場合は、それぞれの自治体で許可を取得しなければなりません。
サポート内容
当事務所では、積替え保管を行わない運搬先から排出先へ直接運搬する「直行型」の許可申請・更新手続き、ならびに各種変更届のサポートを行っております。
許可取得の要件
許可を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 産業廃棄物処理業講習会の受講
- 一定の財務基盤があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 事業計画書の作成(収集運搬方法などを具体的に記載)
| 業務内容 | 報酬(税込) | |
|---|---|---|
| 新規 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請 ※1機関 | 121,000円~ |
| 更新 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請 ※1機関 | 88,000円~ |
※上記金額は目安です。正式な金額はお見積りにてご提示いたします。
※申請手数料などの実費は別途必要です。
古物商許可申請

中古品やリサイクル品の売買を行うには、警察の古物商許可が必要です。当事務所では、初めての方でも安心して手続きを進められるよう、書類作成から管轄警察署への申請まで一貫して対応いたします。
古物商の許可とは
最近では、メルカリなどを通じた古物のやり取りが日常的に行われるようになっていますが、こうした取引については、通常、行政の許可などは特に必要とされていません。
古物営業許可が不要なケース
- 自分で使う目的で購入した物を売る(使用済み・未使用にかかわらず)
- 新品を購入して、そのまま販売する
- メルカリなどのオークションサイトで、自分の所有物を出品して売る
- 無償で譲り受けた物を販売する
- 一度売った相手から、同じ物を買い戻す
- 海外で自分自身が購入した物を国内で販売する
古物商許可が必要になるケース
- 古物を買い取って販売する、あるいは修理して販売する
- 古物を買い取り、その一部を部品として販売する
- 古物を買い取らずに販売し、その代わりに手数料を受け取る(委託販売)
- 古物を他の物品と交換する
- 古物を買い取ってレンタル事業に活用する
- 国内で購入した古物を海外へ輸出する
- 上記のような取引をインターネット上で行う場合
出典:警視庁公式サイト「古物営業」より
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/
サポート内容
必要書類の収集
(住民票、身分証明書、法人の場合は履歴事項全部証明書など)
申請書や誓約書の作成、ご用意いただく添付書類のご案内
警察署との事前相談の実施
書類一式の最終チェック
警察署へ予約のうえ申請書類を提出し、手数料を納付(当方で立替または預かり金による対応)
受領証明書の交付後、副本および控え書類をご依頼者様に送付
申請が受理されてから、およそ40日前後で許可が下りる
申請者本人による警察署での許可証受領
※実費として、警察署にて法定費用(19,000円)の支払いが別途必要です。
| 項目 | 報酬(税込) | |
|---|---|---|
| 個人 | 古物商許可申請(新規) | 38,500円~ |
| 法人 | 古物商許可申請(新規) | 49,500円~ |
※上記金額は目安です。正式な金額はお見積りにてご提示いたします。
※申請手数料などの実費は別途必要です。
相続手続き

ご家族の急な相続や、遠縁の複雑な手続きを任された方へ。
高齢の相続人や多忙な方に代わり、当事務所が相続手続きをサポートします。
相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や遺産分割協議書等が必要です。
戸籍謄本の収集は想像以上に複雑で、つまずく方も少なくありません。慣れない方には大変な作業を丁寧にお手伝いいたします。
| 業務内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 相続手続きのご相談(1時間) | 5,500円〜 |
| 相続手続きまるごとサポート (相続人調査、関係説明図、財産目録、遺産分割協議書作成、名義変更など) | 220,000円〜 |
| 戸籍取寄せプラスコース (相続人調査と相続関係説明図の作成含む) | 44,000円〜 |
※上記金額は目安です。正式な金額はお見積りにてご提示いたします。
遺言書作成

遺言書は、ご自身の意思を正しく残し、相続トラブルを防ぐための大切な手段です。当事務所では、初めて遺言書を作成される方でも安心して進められるよう、丁寧にサポートいたします。
遺言書作成のポイント
- 遺言書の種類(自筆証書遺言、公正証書遺言など)に応じた作成方法
- 相続人や財産の整理、分割方法の検討
- 法的に有効な文章の作成と記載内容のチェック
サポート内容
- 遺言書の種類や作成方法のご提案
- 内容の整理や法的要件の確認
- 公正証書遺言の場合、公証役場での手続きサポート
複雑な手続きや法律の不安も、分かりやすく丁寧にご説明し、最後まで責任を持って対応いたします。初めての方でも安心して遺言書を作成できるよう、しっかりとサポートいたします。
| 業務内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 自筆証書遺言の内容チェックサポート | 33,000円〜 |
| 自筆証書遺言の作成サポート | 55,000円〜 |
| 公正証書遺言の作成サポート (※公証役場の手数料が別途必要です) | 77,000円〜 |
※上記金額は目安です。正式な金額はお見積りにてご提示いたします。
※上記の報酬とは別に、戸籍謄本や登記簿謄本などの実費がかかります。
※金額はすべて税込で表示しています。